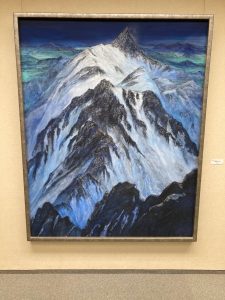NHK文化センター柏教室のHさんの作品をご紹介します。
平鉢の欠けの金繕いです。
こちらの器はご友人が骨董店からお求めになったのを依頼されて
金繕いされた物です。
アップの画像を見て頂くと、その形に違和感を覚えられるのでは
ないでしょうか。
そう、通常よく見る欠けとは違う形なのです。
これは骨董店が欠けていた部分にヤスリをかけて窪みを目立たなく
加工してしまっていたことによって生じた形だからです。
確かに形として目立たなくなりますが、素地を守っている釉薬を
削り落としてしまっているので、器としては不完全なものになって
います。
金繕いするにあたってHさんは釉薬だけでなく、形として損なった
部分も補って直されました。
本来の姿に戻すのは意外に大変で苦労されましたが、丁寧に直された
器は喜んでいるのではないでしょうか。
金泥の光沢がひときわ輝いて見えます。
骨董業界では破損がないものを「完品(カンピン)」と呼び、破損
しているものは一段低く見られます。
金繕い(金継ぎ)の流行で破損しているものを敢えてお求めになる方も
多くなりましたが、かつては隠すように展示されていました。
それが故に小手先の加工で販売されたのだと思いますが、金繕い
(金継ぎ)が流行しているからこそ、手を加えずに販売して頂けたらと
願って止みません。