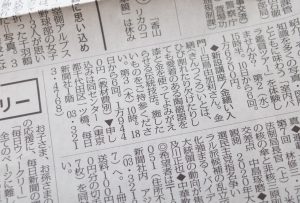カテゴリー別アーカイブ: 日常の風景
横浜山手西洋館 花と器のハーモニー2019
毎年出かけている横浜山手西洋館のイベントに出かけてきました。
今年のテーマは「開港160年 山手今昔 想いを馳せて…」です。
●山手111番館 classical1926〜modern2019


●ベーリック・ホール Jeux de Fleurs -花遊び-


●ブラフ18番館 flowers born from wood


全体の感想としては、かなり満足感があったと言えます。
館それぞれが鮮やかな花の色に飾られていて楽しめました。
特に男性の華道家が多かったせいか、空間をダイナミックに使った花活けが
印象的でした。
私なりのベストを選ぶとすれば、横浜市イギリス館でしょうか。
色合いが綺麗だったことと、寝室のコーディネートが今までにない感じで
記憶に残りました。
会期は今週末9日日曜日までです。
周辺の港の見える丘公園や山手イタリア山公園も花がいっぱいですので、
散策も楽しいかと思います。
是非お出かけ下さい。
福々しいトクサの新芽
ピラティスを教えて頂いているMidori先生から譲って頂いたトクサが
福々しい新芽を出しています。
大トクサに見間違えたのかと思うほど立派な新芽なので、思わずMidori先生に
遺伝子が違うのですか?と質問してしまいました。
勿論、遺伝子の違いではなくて、Midori先生が私に株を渡す前にしっかり肥料を
与えていたからなのです。
総じて地植えより鉢植えの株の方が育ちがはかどらないものなのですが、肥料の
効果がこれほどとは思いませんでした。
トクサの育て方については、お悩みの方が多いので、しっかりMidorim先生に
ご教示頂き、皆様にもお伝えしたいと思います。
藍の発芽2019
先日蒔いた藍の種が芽を出しました。
発芽時期は種を蒔いてから7〜10日なのですが、それを守ってきっちり
7日後から発芽しだしました。
11日目に当たる今日までで何と100%の発芽率でした。
しかし発芽時点で後々大きく育つものは双葉からして大きいのですが、あまり
大きくないものは小さいままです。
最終的には6株でいいのですが、念の為、さらに8粒蒔いてみました。
昨年は天候によってアクシデントがあったので、時期をずらして種を蒔くのが
防御策になるかと考えています。
さて、どうなるか。
あまり神経質にならずに観察したいと思います。
急遽 藍の種蒔き
今秋、自宅マンションの大規模改修があるので、藍の種蒔きは
しないつもりでした。
それが工事が来春に延期となる可能性が大となり、急遽種を取り寄せ、
蒔きました。
昨年は種を蒔いた後に真冬並みの寒さが来たりして発芽が良くなかった
のですが、さすがに5月中旬になっているので、そのような問題は
なさそうです。
そういうことを前向きに考えて、昨年の反省点をクリアして、うまく
育てられたらいいなぁと考えています。
線香作り
西登戸教室をお借りしているKさんには、お香を匂い袋、練香と
教えて頂いてきましたが、今回はお線香を教わってきました。
匂い袋、練香と同様に使う素材を聞き、自分のイメージに合わせて
調合していきます。
それを水で練って注射器に入れて出す細い棒状とコーン型に成形
しました。
これをしっかり乾燥させて完成です。
実際火をつけて聞いてみたところ、狙いの「すっきりした甘め」になって
おり、なおかつ天然素材なので上品な香りで、かなりの満足度です。
香りは焚いている時ではなく、燃え尽きてしばらく経ってから残り香を
楽しむものなのだそうですが、時間の経過で変化していくのも面白いと
思いました。
調合の仕方で全く違う香りが出来上がりますし、何より天然素材なので
プレゼントにもいいのではないでしょうか。
是非またチャレンジしたいと考えています。
金繕いは再構築
たまたま見たNHKの「デザイントークス+(プラス)」という番組が
「再構築」というテーマでした。
このデザイントークス+という番組は、「デザイン力ってなんだろう?」
という好奇心をもとに形に宿る精神、哲学をひも解きながら日本のデザイン
の世界を探求するものです。
再構築というテーマは、デザイナーの吉泉聡さんを迎えて、これまでのモノと
人との関係を再構築するようなデザインについて語られていました。
再構築というのは、例えばすでにある製品に新たなデザインを加えて新しい
プロダクトを生み出すことを指しています。
この論議の中で金継ぎ(金繕い)が出てきました。
MCの金継ぎにも興味はあるかとの問いに、吉泉さんはあると答えます。
金継ぎ(金繕い)は破損したというマイナスの状態をプラスに再構築する
ものだという吉泉さんの説明に腑に落ちるものがありました。
元は職人の技術であった金繕いが今や「kintugi(金継ぎ)」で海外に通用する
ようにまでなったのは、単にもったいない精神を超えて新たな意匠をまとった
ものに蘇らせる「再構築」に魅了されたからではないでしょうか。
かく言う私も金繕いの再構築に魅了された一人です。
作品画像
お教えしている教室で撮影させて頂いた作品画像を整理しています。
改めて見てみると、数えきれない状態になっていました。
都度、ブログでご紹介していますが、他の教室の方の参考になるのは
もちろん、励みになったりと当初は想定していなかった効果があるように
思います。
「完成した作品を先生に撮影させてと言われるのが目標だった。」とおっしゃって
下さる方もありました。
撮影をお願いすると、どなたも快く応じて下さり本当に感謝しております。
画像は私にとりましても貴重なデータです。
どうぞ今後も撮影にご協力下さいますよう、お願い致します。
ゴールデンウィーク2019
例年、ゴールデンウィークは自宅で過ごすことが多いのですが、
今年も自宅中心になりました。
10連休も新元号も関係なしです(笑)
ちょっと外出したのが、最近近隣に出来たカインズホーム です。
東急ハンズに始まり、DIYショップは大好きなのですが、カインズホーム には
初めて入りました。
びっくりしたのがDIY女子が好みそうな道具・材料コーナーです。
おしゃれな道具類から材料まで、ワクワクする品揃えです。
どちらかというと専門家仕様のビバホームやコーナンと違い、エンドユーザー向け
の店構えはなるほどと思いました。
まだ開店したばかりなので、店舗内も綺麗です。
思わず端から端までチェックしてしまいました。
こういう時の観察がどこで役に立つかわからないので、趣味と実益を兼ねて
おります。