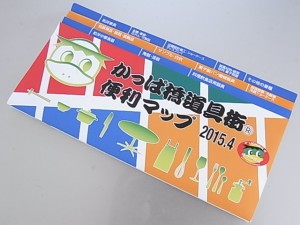カテゴリー別アーカイブ: 日常の風景
大宮教室 体験講座終了しました
本日、よみうりカルチャーセンター大宮教室での体験講座
「金つぎの技法を知り、蒔絵体験」が終了しました。
以前から金繕いをご存知で、やってみたいというお気持ちの
強い方々にご参加頂き、ご説明する私も充実感を感じる
講座となりました。
撮影させて頂けた方の作品をご紹介したいと思います。
今回ご参加の方々は、少ない枚数を効果的に配置し、シンプルに
まとめられたのが印象的でした。
体験講座は金繕いの本講座では、なかなかお話が出来ない金繕いの
歴史として、興味深い逸話のある過去の名品についてご紹介
しています。
ご都合が合いましたら、是非ご参加下さい。
今後は7月31日にNHK学園市川オープンスクールで予定があります。
(残席あとわずかです。)
新規開講の教室に伴い、体験講座を計画することが多いので、都度
お知らせ致します。
かっぱ橋案内2
昨日に引き続き、かっぱ橋案内をしたいと思います。
地下鉄銀座線「田原町」から、かっぱ橋へは和食器の「田窯」の
ところから折れて入ります。
田窯の並びは「西浅草地区」と呼ばれ、合計83店舗あります。
この中に食器を扱う店舗は、18軒ほどです。
言問通りにあたったところで折り返ししますが、以前にもご紹介
しました「合羽橋珈琲」で、休憩するのが定番です。
かっぱ橋には女性が入りやすい感じの食事とお茶ができるお店が
少ないように思います。
私が入ってもいいと思えるのは、この合羽橋珈琲ともう1軒くらい
です。
今回はガトーショコラで糖分補給です。
折り返して、道路の反対側は「松が谷地区」と呼ばれます。
こちらにある食器関係のお店は、18軒ほど。
かっぱ橋には、何かに特化したお店ばかりですが、特に私が面白い
と思っているのが、ガラス瓶や缶を取り扱う「高村製缶」さん。
竹製品専門の「近藤商店」さんです。
テレビでもよく紹介されている料理道具の「釜浅商店」さん。
店舗前の釜が目印です。
こういう特化したお店は独特のこだわりがあって、見ていると楽しく
なります。
そもそも私がかっぱ橋に行くようになったのは、体験講座の教材費を
出来るだけ押さえる為でした。
蒔絵体験をして頂くのによいお皿を探すのが目的です。
体験の為のお皿には条件がいくつかあるので、コストも加味すると
なかなか厳しいものになります。
今年に入って、その条件に適うお皿が見つかりずらくなりました。
白いお皿の流行の影響もあるかもしれません。
他の方法を探さなければならないのかと考えているところです。
かっぱ橋案内1
体験講座の準備の為、またまたかっぱ橋に買い出しに
出かけました。
ご興味がある方がおられますので、少々ご案内をしたいと
思います。
かっぱ橋に行くにはいくつかのルートがありますが、私は銀座線の
「田原町」を利用しています。
駅から浅草通りを上野方向に歩いて5分程度です。
浅草通りは、仏壇•仏具店が多いことでも有名ですね。
HPもありますが、店舗に置いてあるマップが便利です。
元は業者向けの街ですから、店舗用の設備や、梱包材、ユニホームなど
一般の方には違う関係のお店もあります。
皆様がご覧になりたいのは、食器類の他、調理道具なのではないかと
思います。
それもグループ分けされたマップで探しやすくなっています。
アーケードになっているので、雨の日も買い回りしやすくなっていますが、
交差点などで途切れるところがありますので、傘がいらないわけでは
ありません。
次回はお店の紹介をしたいと思います。
成田教室 開講しました
TOPページでお知らせしていましたセブンカルチャー成田教室が
昨日開講しました。
最寄り駅は京成線公津の杜駅です。
初回は主に下準備の説明と、修復ご希望の器の診断に時間を費やす
のですが、熱心に受講して頂き、ご受講の皆様に御礼申し上げます。
3回目まで基本の技術に関しての説明が続きますが、不明の点は都度
質問して頂き、じっくり取り組んで頂ければと思っています。
手間、時間はかかりますが、それに見合う、納得の仕上がりを目標
としています。
どうぞよろしくお願い致します。
若生おにぎり
青森のお土産として「若生(わかおい)昆布」を頂きました。
若生昆布とは薄く柔らかい1年ものの昆布のことです。
津軽半島沿岸で冬場に採取され、干してあります。
これで作ったおにぎりが、郷土料理として現地で親しまれて
います。
磯の香りが素朴な味わいです。
面白いのが、繊維に沿って食べないと噛み切れないところです。
珍しい物を楽しんで頂きました。
バリアフリー字幕•音声ガイド
友人の岩佐さと美さんが、フリーの翻訳家として仕事を始めるに
あたって、名刺の版下作成をさせてもらいました。
彼女の仕事の中で、とても興味深く話を聞いたのが、「バリアフリー
字幕•音声ガイド」というものです。
バリアフリーというと、建物の中で段差がないという対応をいうのが
一般的な認識だと思います。
これが翻訳の世界では目や耳に障害のある方でも映像コンテンツを楽しむ
為にサポートするものを作成する仕事だということです。
例えば目が不自由な方には、脚本のト書きのような文章を作成し、音声
ガイドとして挿入するというような対応です。
岩佐さんは、翻訳を勉強中に目の不自由な方がバリアフリー音声ガイドに
よって映像を楽しまれ、「こんなに楽しい世界があったとは!」と感動
されていたのを見て、この分野での仕事を志したそうです。
日本ではまだまだの分野ですが、アメリカではこのような対応をしたものが、
当たり前になっているのだとか。
何の不自由もない私たちが当然のように享受している娯楽ですが、それが
障害を持った方々にも同じように提供される…そんな成熟した文化を持ちたい
と思いました。
※岩佐さんの仕事にご興味を持たれた方は連絡を中継しますので、「お問い
合わせ」フォームからご連絡下さい。
キャリーバッグ世代交代
長年仕事の相棒だったキャリーバッグがキャスターが摩耗して
しまって、ついに引退を余儀なくされました。
なるべく実物サンプルをご覧頂けるよう、たくさん荷物を詰め込み、
いろいろな教室に出かけました。
あまりにいろいろな道具が出てくるので、「ドラえもんのポケット」
かと思われるくらいでした。
新しいキャリーバッグは、ポケットの数が減ってしまいましたが、
撥水加工で少々の雨なら大丈夫ですし、軽量化されているので、
持ち運びの負担が減りそうです。
これからも参考作品など、教室にお持ちします!
貝の記念切手
切手のコレクターではないのですが、6月5日発売の記念切手が
貝殻だったので、郵便局に出かけました。
奥に写っているのが、港北カルチャーセンターでの「自然の貝で貝香合
つくり」でも使って頂きます「ヒオウギガイ」です。
切手にあるオレンジと紫の他、赤、黄色などもあります。
表面の色が内側にも反映されますので、作品作りは色を生かして作ることが
出来ます。
手前の白地にピンクの筋がある貝は「ネコジタザラガイ」です。
これは作品に仕立てているので、教室でご覧になった方もおられると
思います。
名前の通り表面に猫の舌のように細かい突起があり、ざらざらしています。
しかしピンクの筋が内側にも透けてとても綺麗な貝です。
貝香合の講座を行っている時に貝殻の記念切手が発売されるとは、何とも
good timing です。
刺繍の道具入れ
いろいろ道具箱をご紹介してきましたが、また素敵な道具入れを
お持ちの方がおられましたので、ご紹介したいと思います。
NHK学園市川オープンスクールのUさんの道具入れです。
Uさんは先般、お手製のペンケース型のものをご紹介させて頂き
ましたが、さらに他の道具を入れる手提げ型のものも自作されて
いました。
愛らしい刺繍もご自身がなさったもので、拝見して思わず「かわいい!」
と言ってしまいました。
中はいろいろ仕分けされた道具が収まるようになっており、コンパクト
かつ機能的です。
深さが浅いので、すぐ必要なものが見つけられそうです。
この日、ユザワヤ津田沼店がどんどん小さくなっているという話も
出ました。
近年手工芸に親しんでおられる方が少なくなっている現れなのかも
しれません。
しかしUさんのように身のまわりの物を自作されるというのは、美しい
生活だと思います。
金繕いも同様です。
簡単に終わらせたいというご要望もあるかもしれませんが、丁寧に
より美しい仕上がりを目指して頂ければと考えております。