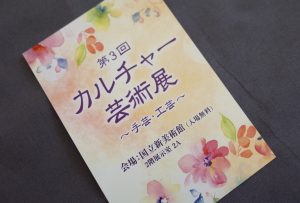柏の葉T-SITEで行った後、リクエストがありまして、またシー陶器や
シーグラスを使って呼び継ぎが体験できる箸置き、アクセサリー作りの
イベントを行うことになりました。

八千代緑が丘教室のTさんの作品
帯止めの金具をつけられました
2022年1月19日(水) 10:00〜11:30
船橋市塚田公民館
参加費:2,300円(材料費込み)
箸置き1個の製作を考えていますが、別売の金具を使ってアクセサリーに
仕立てることも可能です。
通常の金繕いの教室では使用しない材料を使って1日で完成させることが
出来ます。
お問い合わせ&お申し込みはトライラボ070-5569-7908
残席3名様です。
ご検討をどうぞ宜しくお願い致します。