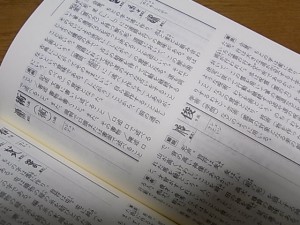カテゴリー別アーカイブ: 日常の風景
スマホ デビュー
いじいじとガラケーを使い続けていたのですが、ついにバッテリーが
立ち行かなくなり、思わぬスマホ デビューとなりました。
最新は6ですが、小振りなiPhone 5sを選択しました。
実は私はAppleファンで、パソコンもMacを使っています。
ご存知の方も多いと思いますが、現在当たり前のように使っている
windowやアイコン、マウスなどは全てApple発祥です。
Appleはデザインは勿論ですが、子供でも使える単純な操作性が
魅力です。
何となくいじっていれば使えてしまうというのは、設計思想が
バリアフリーだからだと思っています。
こう書くとヘビーユーザーのようですが、「持ってると幸せ」という
単なるファンです。
という訳でスマホに適応出来るのか、早くも不安です。
大丈夫か!?
代用成功
ナチュラル系の雑貨店で購入した掃除用ブラシを、拭き漆の
道具として使ってみました。
本来の漆刷毛は、下の画像のようなものです。
これは本漆を綺麗に均一に塗り上げられます。
しかし拭き漆では、それほど厳密でなくてもよいと考えました。
雑貨店で買って来た掃除ブラシは、面相筆がたくさん植わっている
ような形になっているので、根元がすけています。
これが本漆を落としやすいのではないかと思ったのですが、まさに
狙い通りでした。
本漆を扱われる方はご存知と思いますが、作業終わりに行う漆刷毛の
始末は、漆で刷毛が固まってしまわないように時間をかけて刷毛の根元を
ヘラで叩いて油で洗浄します。
これがなかなか大変な作業であることは勿論、また作業を始める時には
油を完全に落とし切っていないと、塗った漆が固化しなくなります。
このブラシはその手間を一気に解決してくれました。
あまり耐久性はないと思いますが、価格が安いので、それも気にならない
と思います。
ずつなし とは
NHK文化センター横浜教室で、横着するという意味で「ずつなし」
という言葉が話題になりました。
京都出身の母方が使う言葉だったので、私はてっきり関西地方の
言葉だと思い込んでいたのですが、古典文学にも出てくる言葉
だとか。
そして本来は「術無し」で、どうにもしようがないという意味
なのだそうです。
このように本来の意味とは変わった意味で使われている言葉は
たくさんあります。
私が最近とまどうのが「大丈夫です。」という若者言葉です。
all right ではなく、No thank you という意味で使われます。
さて皆様は、このようにとまどう言葉はありませんか?
徐々に均一化
今夏塗り直しに取り組んでいたレンゲですが、塗っては削りを
繰り返して徐々に均一になってきました。
またツヤが出過ぎているところに紙ヤスリをかけて、拭き漆をして
いく予定です。
ヒビが入っていたのを止めた部分ですが、馴染んでしまってほとんど
わからなくなりました。
少し手順が遅れたスプーンの方は、まだまだ斑状態ですが、
根気よく作業していればきっと綺麗になってくると思います。
生藍染め用白生地購入2014
葉の生育がイマイチな今年の藍ですが、何とか1回の染めを
行うべく白生地を購入してきました。
帯揚げ用の生地で、細かい縮緬が入っています。
難ありですが、飾り座布団が目的なので、お買い得と言える
でしょう。
購入先は昨年同様「誠和」さんです。
生藍染めにチャレンジしたら、またレポートします。
煙る横浜
今日はNHK文化センター横浜教室の助手の日でした。
10月上旬並みに寒く、小雨が降った横浜。
ランドマークタワーが雲で霞んでいました。
暑さに疲れてはいましたが、ここまで涼しくなってしまうと
身体が驚いてしまいます。
皆様体調には気をつけて、教室にお出で下さい。
鈴焼
和歌山県のおみやげで、「鈴焼」(香梅堂)というのを頂きました。
入手が大変難しいお菓子だそうです。
甘党なので、お菓子の頂きものはとても嬉しいのですが、貴重なもの
となると尚更です。
じっくり味わって頂こうと思っています。
喫茶店エレーナ
商業施設が充実している神戸の異人館街と違い、横浜の西洋館は
住宅街の中にある洋館を、当時を想像して頂きながらご覧になれるのを
旨としています。
そのため見学の際には、ランチやお茶休憩する場所を考えておく必要が
あります。
私がオススメなのが、「喫茶店エレーナ」です。
西洋館が集中している港の見える丘公園から元町公園あたりまでと、
イタリア山庭園の間に位置しています。
JR石川町駅から山手に登り、ブラフ18番館と外交官の家を見学。
エレーナで昼食を摂って、午後元町公園方面へ行くパターンと、
みなとみらい線の元町中華街駅から山手に登り、山手111番館、
イギリス館を見て、元町公園付近で昼食、その他の館を見学して、
イタリア山庭園の途中でエレーナでお茶というのもいいと思います。
エレーナは、季節の紅茶とスィーツがメインですが、カレーやスパゲッティ
などの軽食も美味しいです。
私が特にオススメしたいのが、サンドイッチなどのパンを使ったランチです。
店主がパンにこだわって手に入れているので、パンが美味しいのです。
特にお気に入りが、ロールパンのサンドイッチです。
高台にあるエレーナの窓からは、港が一望できます。
この景色を見ながらの休憩は、他では得難いものです。
横浜山手においでの際に、お店を探してみて下さい。
ベーリック•ホール パームルームの謎
昨日に続き横浜山手西洋館について、お送り致します。
横浜•山手にある西洋館の中で、最大規模を誇るのが「ベーリック•ホール」
です。
ベーリック•ホールには居間の北側に、サンルームのように見える
「パームルーム」という部屋があります。
では何故サンルームではなくて、パームルームなのか?
インテリア様式に詳しい友人の助けを借りて、その謎を私なりに
考えてみました。
そもそもサンルームは、16世紀のドイツから始まる温室に起源があります。
「オランジェリー」と呼ばれたオレンジを冬越しさせる施設は、18世紀には
社交のための場〜ダンスパーティー会場と変化します。
オレンジや南方の植物は、社交の場を飾るエキゾチックな装飾の一部だった
のです。
19世紀になると熱帯地域の植民地から次々に有用植物や、鑑賞用植物が
持ち帰られます。
それらを育てる施設として温室は、巨大化していきます。
これは産業革命による技術革新で得られた鉄、ガラス、水蒸気による暖房
なくして成立しません。
(例 イギリスのキュー植物園 パーム•ハウス)
巨大化した温室はその後、健康志向の高まりからサンルームとなり、一般
家庭に取り込まれます。
それが20世紀に日本に伝搬し、和洋併立の住宅に併設されます。
(例 東京•岩崎邸)
ではパーム(ヤシ)とは、何なのか?
一つは、温室の代名詞ということが言えると思います。
パーム(ヤシ)は、温室を飾った熱帯植物の代表です。
そしてその温室は、所有者にとっては経済的な余裕を誇示するステータス
シンボルなのです。
そしてもう一つ、パーム(ヤシ)は、様々な宗教、人種の中で、特別な
植物だということです。
これは日本人にとっては少々縁遠いのですが、言い換えれば「生命の木」
という感じでしょうか。
立ち戻ってベーリックホールを考えてみます。
施主のB.R.ベリック氏は、フィンランド領事の顔を持つ公人でも
あったので、パーティースペースやディナー後のティースペースが
必要になったと思われます。
建築家のJ.H.モーガン氏は、流行の建築スタイルに精通しながらも
居住性を重視する建築家であったことから、ベリック氏の執務室を
兼ねた居間の通風、採光を重視したことが考えられます。
これを眺望の良い2階北側ベランダを支える場所としてサンルーム
様のスペースとしたのではないでしょうか?
場所としては北側なので、サンルームではなく「パームルーム」。
パーム(ヤシ)が特別な植物であることを踏まえれば、パームが
出てくるのは自然な発想ではないかと思います。
ベーリックホールのパームルームには、壁泉と呼ばれる噴水があります。
これは世界的にも珍しい例だと聞きます。
ベーリックホールにお立寄になられた際には、ぜひパームルームを
ご覧下さい。
そして私の推論を思い出して頂ければ、嬉しいです。