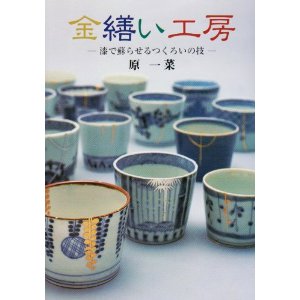カテゴリー別アーカイブ: 基本のき
ガラスも修復できます
金繕いの教室で驚かれるのが、ガラスの修復もできる
ことです。
画像は現在私が修復中の薩摩切子です。
画像では見えない反対側から破片を接着しています。
陶磁器とガラスの修復が違う点はいくつかありますが、
見た目でお分かり頂けるのが「透ける」というところです。
その為独特の処理をすることがありますが、破損の状態
で対応を変えております。
受講を初めてから半年くらいで、ガラスの修復も始め
られますので、修復希望の品がありましたら、一度
教室にお持ち下さい。
洗浄用薄め液の扱い
薄め液の扱いについても、金繕いの教室でよく質問を
受けます。
薄め液は、元々のボトルに入っているものとは別に筆や道具を
洗浄する用のものを別にして頂いています。
この洗浄用ですが、使っていくと赤漆の色で染まっていき、
いずれ底に固まりとなって沈みます。
そうなったら薄め液の上澄みを、一旦別の入れ物に移します。
そして底に沈んだものを掃除して、上澄みを戻します。
底に沈むまでの赤漆による染まりですが、常に洗浄して減った
分を補充していけば、あまり気にならないかと思います。
これを注ぎ足し注ぎ足しして伝えられる『老舗の秘伝のタレ 』
方式と言っています。
ところで薄め液のボトルを 洗浄用として流用している場合、
中蓋が開けにくい上、ちぎれてしまう方が多いようです。
自宅に置いたままにしているのなら中蓋は必要ありませんが、
持ち歩く場合、中蓋があった方が漏れの心配がなく安全です。
中蓋の開け方のコツは、同じ所を引っ張り続けないこと。
少しづつ場所を変えながら、上へ持ち上げるのが肝心です。
貝合わせ 金箔貼り後
金繕いのカリキュラムの中にあります『貝合わせ』は、
金箔のあしらいを勉強して頂く為に行っております。
金箔を貼ったあとの貝は、絵を描いて頂いても構いません。
金繕いにおいては、金箔が使えるようになると仕上げの
バリエーションが広がります。
ぜひ身につけて頂きたい技術です。
3月3日の雛祭りまで、大きめのはまぐり貝が出回りますので、
お買い求め頂き、このカリキュラムの準備をお願い致します。
ふぐ印
金繕いの教室で使用しているのが、櫻井釣漁具の新うるしです。
そのブランド名が『ふぐ印』
店舗は、東京•神田 の今川橋交差点そばにあります。
漆や薄め液、筆類はこちらで販売しています。
この直営店の他、東急ハンズや、釣り具店でも取扱いがあります。
私の方でも販売はしておりますが、月一度しかお会い出来ませんので、
お急ぎの場合は、こちらへどうぞ。
代金引換で、宅急便もしてくれます。
蒔筆について
金繕いの教室で質問が多いことの一つが、蒔筆の扱いについてです。
仕上げの作業のあとは綺麗に払う程度で、洗う必要はありません。
金•銀泥で筆を分けることもないのですが、気にされる方は
分けておられます。
あらかじめご依頼頂ければ教室で販売も致しますが、もしご自分で
購入されるのでしたらデザイン用の平筆をお求め下さい。
蒔き放ちの技法の場合、まだ柔らかい漆の上に金•銀泥を蒔きますので、
羊のような柔らかい毛の筆が必要です。
また平筆の方が、作業効率がいいと思います。
ところで冒頭で洗わなくてもよいと書きましたが、これはあくまでも
漆や金•銀泥で汚れなかった場合の話です。
もし仕上げの作業の際に漆などがついてしまった場合は、薄め液で
洗ったあと中性洗剤で洗浄して下さい。
このところ漆や金•銀泥で汚れたまま、コテコテに固まってしまった
筆で仕上げをされ、芳しくない結果(全体がマットになり、ゴミが
入り込む)になっておられる方が数人見受けられました。
せっかく頑張って仕上げまできたのに、もったいないことです。
蒔筆は特に清潔さが肝心です。
洗ったあともゴミが付かないように工夫して保管して下さい。
今、このブログを読んで、ご自分の蒔筆がコテコテに固まっている
ことに気がつかれた方!諦めるのは早いです!
その筆をしばらく薄め液につけておいて下さい。
15分から30分も浸けますと、固まっていたのがゆるんできます。
爪先で汚れ、漆の固まりをほぐし落として下さい。
(この時穂先を引っ張らないことがポイントです)
その後、中性洗剤で洗って下さい。
筆が復活致します。
内外同時進行
本日が金繕いの作業の仕事始めになりました。
今日は依頼品に赤漆を塗り重ねる作業をしています。
金繕いの作業は、このように下地作りの作業が大半です。
ところで器の高台に疵がさしかかっている場合、内側だけとか
内側外側交互に作業するなど効率が悪くなっていませんか?
下地の作業の場合、内外同時に作業したいところです。
画像は接着した器の欠損を赤漆で埋めているところですが、疵が
高台にさしかかっているので、内側外側同時に作業する場合は下に
角材を入れて作業面が触れないようにしています。
割り箸で十分代用出来ますので、同時進行の作業の際には使って
みて下さい。
12月に接着をされた方は、次にこの赤漆の作業に移りますので、
覚えておかれるとよろしいかと思います。
豊作
以前のブログに書いた通り、金繕いの作業で使うトクサの収穫を
しました。
豊作です。
今年はマメに肥料を与えた効果が出て、緑色も濃く、しっかりした
トクサが収穫出来ました。
枯れてしまった部分を取り、太さを選定して、あとは乾燥させる
だけです。
刈り取ったあとの鉢は、まるで稲刈りのあとのようです。
来春また新芽が出てきますが、根が鉢一杯になっているので
株分けする予定です。
注 私は鉢で育てていますので、適度に肥料を与えていますが、
地植えしている方は殊更肥料を与える必要はありません。
呼び継ぎとは
金繕いの技法のひとつに「呼び継ぎ」があります。
これは割れた器の破片が一部足りない場合、他器の破片を
利用して埋めたものを言います。
この日本独特の感覚の呼び継ぎには過去名品が数々ありますが、
私が好きなのは「織部よびつぎ茶碗」です。
この器は美濃焼の陶芸家•荒川豊蔵氏の旧蔵品で、かの白州正子も
気に入りの品であったそうです。
以前のブログでも書きましたが、呼び継ぎを行うには径、厚み、そり
などがあった破片がなくてはなりません。
さらに色、文様が合うとなると、選択がかなり難しくなります。
一朝一夕に出来る物ではありませんので、根気よく破片を入れる器と
破片が揃うのをお待ち下さい。
なお昔の窯跡から陶片を持ち出すのは法律で禁じられておりますし、
現代の窯元や陶芸家の破片も必ず承諾を得てから入手して下さい。
よく敷地に破片が打ち捨ててありますが、ゴミではなく、作家さんの
作品の一部であることには変わりがないのです。
インスタグラム「kintsukuroi shiratori」
トクサの色
先日金繕いの教室で、トクサの色についてご質問を受けました。
トクサを刈り取って乾燥させても、なかなか枯れ色にならない
というものです。
左のような色を「枯れ色」というのですね。
お問い合わせのように、画像のような枯れ色になるにはかなり
時間がかかります。
右の少し緑が残っている状態でも、3ヶ月ほど干しています。
しかし色はトクサの性能には関係ありません。
要はトクサが土壌から吸い上げた硅素が、乾燥させることによって
表面に結晶化すればいいのです。
以前のブログに書いたように、1週間乾燥させれば使用可能な
状態になります。
江戸時代はトクサを塩ゆでにして開き、板に貼付けたそうですが、
金繕いではそこまでする必要はないと思います。
原一菜先生の著書
いくつかのお教室ではご紹介しておりますが、金繕いの教室は
原一菜(はら いちな)先生の著書『金繕い工房』に準拠して
行っております。
この本は教室でお教えしている内容の補完になるばかりでなく、
金繕いの歴史や、上絵付けの文様の考え方など、技法書というより
教養書と言える濃い内容になっております。
ご理解頂きたいのは、本の説明は教室でご説明しているより安全を
みた方法で解説されているということです。
これは 技術という物は本来口伝で伝承されるものですので、本のみ
ご覧になって金繕いを試みられる方には、そうせざるを得ないからです。
教室にご参加頂いている方には、それぞれ直したい器に合わせて
より詳しく手順•コツなどお話しています。
なお大変申し訳ありませんが、この本を教室で販売してはおりません。
書店•ネットなどでご購入頂ければ幸いに存じます。
(出版社:里文出版 価格:¥2,625)
※私共一菜会としては『金繕い』が古来からの本筋の言葉と
考えております。
金継ぎとは、近代に発祥した金繕いと同じ意味の言葉です。