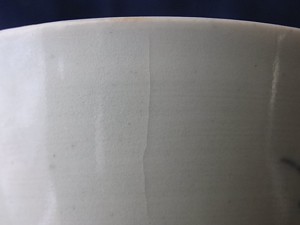カテゴリー別アーカイブ: 基本のき
和食器=陶器?
金繕いを始める際に重要になるのは、陶器か磁器かを見極め、
下準備をするかしないかを判断することです。
よく和食器=陶器、洋食器=磁器と考えている方が多いのですが、
これは誤りです。
和食器、洋食器というのは用途の区分で、素材とはイコールには
なりません。
陶器と磁器の判別の仕方は以前のブログに書いていますが、改めて
整理してみたいと思います。
陶器は土を固めて、ガラス質の釉薬を掛けて焼成したものです。
釉薬の掛かっていない高台裏には土の茶色が見えています。
低い温度で焼かれているので、叩くと鈍い音がします。
磁器は石の粉を固めて、ガラス質の釉薬を掛けて焼成したものです。
釉薬の掛かっていない高台裏には石の白い色が見えています。
高い温度で焼かれているので、叩くと金属質の高い音がします。
陶器は下準備が必要ですが、磁器はほぼ不要です。
スムーズな出だしのために、どちらなのか判断出来るようにして
おくとよいと思います。
仕上げは難しい?
NHK文化センター柏教室のMさんの作品をご紹介致します。
縁が数カ所欠けた大鉢です。
Mさんは欠けを埋めるのが大変上手で、それぞれの形がきれいに
復元されています。
こちらは数カ所ひびが入ったカップです。
仕上げの線の太さがカップに合っているので、複数の仕上げが気に
なりません。
2点仕上げてみたMさんの感想は、欠損を埋めるより仕上げが難しい
ということです。
前回仕上げて来られた時も同様の感想をおっしゃっていましたが、
何度もやり直されるのがMさんの素晴らしいところです。
確かに欠損を埋めるのは根気よく続けていれば、必ず埋まっていきます。
仕上げは1回蒔下を塗って、金•銀粉を蒔いてしまえば完成するように
思えます。
しかし実際は上手く完成するために気をつけなければならないポイントが
あり、簡単に出来るものではありません。
敢えて言うなら「画竜点睛」です。
ただ恐れていては再び使うという金繕いの目的は果たせません。
ぜひ積極的にチャレンジしてみて下さい。
厚塗りは駄目
新うるしでの金繕いの基本は、弁柄の薄塗りです。
「たくさん塗って早く埋めようと思って」とか「金がしっかり
定着するかと思って」とおっしゃって厚塗りする方がおられます。
厚塗りしても問題が起きなければお好みでとお話出来ますが、
確実に問題が起きるので、絶対にお勧め出来ません。
基本はあくまでも薄塗りです。
薄塗りを練習するなら、欠損を埋めるために塗り重ねを行う時を
利用するのが一番です。
どの程度塗ればどのくらいになるのか、確認しながら作業してみて
下さい。
蒔筆 洗う?洗わない?
たびたびブログに書いている蒔筆のことですが、このところ
質問が続きましたので、改めて書いてみたいと思います。
まずは洗うか、洗わないかということですが、通常は洗いません。
金•銀泥を払って、塵埃が付かないようにしまいます。
但し金泥を蒔筆にしっかりまぶさず仕上げをしてしまい、新うるしと
金泥が混ざった状態で筆の先に付いてしまった時には洗う必要が
あります。
このような状態のまま仕上げを行うと、仕上げた面が光沢が
出ません。
15分ほど洗い用の薄め液に浸けて、爪で汚れをほぐし落とすと
元通りにきれいになります。
なお金•銀泥で筆を分けた方がいいかという質問も多いのですが、
分けなくても問題はありません。
ただ同時に金泥、銀泥の仕上げを行いたい時には2本持っていると
便利ではあります。
お考え次第で、ご検討下さい。
トクサ 枯れた部分は使えない
このところ多い質問が、トクサの枯れた先端は使えるかという
ものです。
これは以前のブログに書いていますが「使えない」という
のが、回答になります。
それはすでに朽ちているからです。
実際使って頂くとわかりますが、ぼろぼろに脆くなっている
はずです。
あらかじめ枯れ色になっているので、そのまま使えると思われる
方が多いのですが、簡単に道具になるものではないのです。
適切な時期に刈り取り、適切な方法で乾燥させなければなりません。
具体的な手順は教室でご質問頂くか、このブログ内を検索下さい。
仕上げのしなおし
セブンカルチャークラブ成田教室のHさんの作品をご紹介
致します。
たくさん仕上げてきて下さいました。
こちらは陶器カップの欠けを金泥で仕上げたものです。
金泥が映えて綺麗です。
こちらも欠けの修復です。
鮮やかな染付け文様に金泥が際立っています。
2点の仕上がりに関して、Hさんは不本意なご様子。
お皿の仕上げは、やり直しを決断されました。
仕上げというと緊張される方が多いのですが、たびたびご説明
しているように、やり直しは難しくありません。
まず仕上げをトクサで磨き直します。
コツは金泥を削り切ってしまわないこと。
それから弁柄の塗り重ねを行って、再びトクサで磨き直せば
よいのです。
上の画像の蕎麦猪口は、線がゆらいでいるのが気になると
いうことでした。
こちらは一部を削って、竹の葉を蒔絵することをご提案して
みました。
さてどのように変化するのか、楽しみにお待ちしています。
「にゅう」とは
金繕いを始めたばかりの方が戸惑うのは、独特の言葉では
ないでしょうか?
その典型例が「にゅう」ではないかと思います。
にゅうとは軽症のひびのことで、器の表面には欠損が現れていません。
ですので爪で触っても引っかかりがないのです。
この言葉は骨董用語で「入」と書き、「にゅう」と読ませている
のです。
実はその骨董業界でも「にゅう」と「ひび」の分類は曖昧でした。
それを原一菜先生が著書で微細なひび割れを「にゅう」と定義した
ことで、現在ではすっかり定着しています。
「にゅう」と「ひび」では修復作業が変わってきます。
作業を始める前に、どちらの状態なのか判断しておくのが重要なので、
言葉として明確に表すのは大切なことだと思っています。
一般の方には馴染みのない言葉ですが、決まり事として覚えて
頂けたらと考えています。
萩焼のカビ退治
温かみのある釉薬をお好みの方が多い萩焼ですが、釉薬の
ない高台がカビやすいとご相談も多い器です。
我が家の萩焼(青萩)も高台付近がカビてしまっていました。
カビ退治の方法をご紹介したいと思います。
まずキッチンハイターなど、漂白剤で脱色します。
脱色と書きましたが、その字の通り、漂白剤は色を無くして
いるだけで、実はカビの菌は死んではいないのです。
ですから何度でもカビてしまうのです。
そこで行うのが煮沸です。
器を鍋に入れて、1分ほど煮沸するだけです。
画像では直に器を入れてしまっていますが、丁寧になさるのなら
下に布巾を敷いた方がよいかと思います。
煮沸後、トングと鍋つかみを使って取り出しました。
そのまま除冷します。
電子レンジで菌を退治する方法もありますが、器が完全に
乾燥していないと、レンジの中で割れてしまう心配があります。
特に萩焼はなかなか水分が切れないので、煮沸消毒がオススメです。
萩焼に関わらず、他の陶器でも可能な方法です。
気になる器がありましたら、お試し下さい。
インスタグラム「kintsukuroi shiratori」
今夏のトクサ2016
春に株分けしたトクサですが、生育状況が思わしくありません。
どうも忙しさにかまけて、水やりが不十分だったようです。
調子が良かった昨年を思い出して、夜の水やりを行ってみました。
肥料の頻度も1週間に2〜3度に増やしています。
数日で新芽が出てきたところをみると、対策は正解だったようです。
トクサを鉢で育てている方は、鉢の下にお皿を敷いて水が溜まる
ようにしておくのをオススメします。
トクサはシダ植物なので、水はとても必要です。
渇水しやすい今時期、この方法は効果が高いようです。
また道具として細すぎる芽は、切ってしまうのもいいかと思います。
そのまま伸ばしていても太くはなりません。
太い芽を育てるために細過ぎる芽は取ってしまった方が、効果が
あります。
削りの作業が多くなると、トクサは手元で育てていた方が安心です。
よりよい道具が育つといいですね。