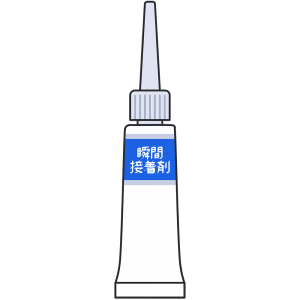カテゴリー別アーカイブ: 基本のき
漂白中
先日、世田谷ボロ市で購入した器を漂白中です。
蕎麦猪口のひびには、まだまだ汚れが入っていますが、だいぶサッパリと
してきました。
漂白で時々ご質問があるのが「漂白して見えなくなってしまったひびは
ひび止めしなくてもいいんですよね。」というものです。
これの答えはもちろん「否」です。
見えなくなったのは、ひびに入った汚れであって、亀裂が入ったという欠損が
直った訳ではないからです。
ひびは先端に水蒸気が入ることによって進行することがわかっています。
金繕いしなければ、そのままひびは進行し、最悪割れに発展するかもしれません。
先日Yahoo!ニュースに割れた器が牛乳で煮ると直るという話題が出ていました。
金繕いを習っておられる方なら、このニュースが荒唐無稽だとお分かり頂けると
思います。
何事も論理的でないことは、あり得ないとお考え下さい。
何のために行うのか真の理由がわかっていれば、作業に迷うことはないと
思います。
美吉野紙の保管方法
伝統的な漆濾し紙の吉野紙に対し、現在一般的に濾し紙として
使われているのが、レーヨンなどの合成繊維で作られた「美吉野紙」
です。
いくつかサイズがありますが、私の購入しているのは28cm ✖️ 54cmの
もので、半紙が長くなったような大きさの物です。
これを仕上げの時に使う場合は、小さくカットして使います。
厳密な大きさの決まりはありません。
半分に切ってを繰り返すと、だいたい7cm角くらいのサイズになります。
この程度の大きさで構いません。
保管は削りカスや紙ヤスリの粉などがつかないように、何らかの袋に入れて
頂ければ良いかと思います。
私は透明のジップ袋に入れています。
仕上げの際には四つ折りにして使います。
のりうるしの時のようにキャンディ型にはしません。
具体的に実演しますので、教室でお問い合わせ下さい。
冷蔵庫で保管
本漆のチューブの保管方法について、ご説明が足りなかったようなので、
改めて書きたいと思います。
基本は立てて冷蔵庫保管です。
冷蔵庫内は本漆が固化しにくい低温低湿の環境であることが大きな理由
ですが、特に生漆や瀬〆と言われる漆の樹液そのもので加工されていない
ものは「なまもの」感覚があります。
漆の固化によってキャップが開かなくなってしまった時は、熱湯の利用で
簡単に開きます。
しかしこれも近日に使用したものでないと不可能になります。
数年キャップを開けていなかった場合は尾部のカシメてあるところを開け、
別途用意した空きチューブに詰め替える必要があります。
カブレの問題を考えると、チューブの詰め替えが簡単ではないとお分かり
頂けると思います。
出来れば使用の都度、キャップについた本漆を拭い、開かなくなるのを
避けるのが一番かと思います。
ちなみに生漆や瀬〆は、開栓後1年を越えると固化の程度が悪くなります。
出来れば早々に使い切る算段をされた方が良いでしょう。
筆が割れる原因
昨年12月にご質問が多かったのが、筆が割れるというものです。
これは以前のブログにも書いているのですが質問が続いたので、
再度説明したいと思います。
ズバリ原因は筆の洗い方が足りないからです。
穂先の根元に漆の成分が残って固まっており、筆を割れさせるのです。
割れてしまうとご質問頂いた方の筆を確認させて頂くと、例外なく
穂先の根元に粘り気を感じます。
場合によっては筆の毛1本1本にまとわりついている弁柄が細い毛の
ようにパラパラと落ちてくる方もおられます。
しかしこれで筆が駄目になってしまうわけではありません。
再度徹底して穂先を洗浄すれば、復活します。
まず薄め液に15分以上、漬け込んで下さい。
その後、画像のように根元を揉みます。
それから通常通り台所洗剤でしっかり洗って頂ければ完了です。
仕上げ用の筆は大切に使えば10年以上持ちます。
メンテナンスにも気配りをお願いします。
ワイングラスの接着
港北カルチャーセンターのMさんの作品をご紹介致します。
ワイングラスの接着です。
かなりガラスの厚みが薄いワイングラスが割れていたのを接着し、
欠損を埋めて、金箔で仕上げて頂きました。
金の線しか見えないので、見た目も綺麗に仕上がっていると思います。
透明のガラスの場合、破損を埋めているのが見えてしまうのが最大の
難問です。
その他、ガラスならではの注意事項がありますので、必ずそれを確認
してから作業を始めて下さい。
これはガラスに限らず金繕い全般に言えることですが、同じように
見えても、工程も同じとは限りません。
同じ受講生の方の話が自分の器の金繕いに使えるとは限らないのが
金繕いの面白さであり、難しさでもあります。
目止め 都市伝説?
先般「目止め」という下準備が、他の作業と混同されやすいという
ブログを書きました。
それと同時に「なぜ行うのか」「どういう場合なら行わなければなら
ないのか」という条件も理解が難しいようです。
「目止め」とは陶器の断面に米の研ぎ汁を使って撥水性をつける方法です。
撥水性をつけないまま金繕いの作業に取り掛かると、接着は着きませんし、
ひび止めではシミが出来てしまいます。
しっかり洗って完璧に乾燥してあれば「目止め」の必要はない
使用していない新品の器の破損であれば「目止め」の必要はない
磁器も「目止め」を行う必要がある
上記の3つは「目止め」に関する誤った認識でよくあるものです。
いずれも何故「目止め」という作業が必要なのか理解されていないが故の
間違いです。
確かに「目止め」の作業は手間がかかるので、回避されたい気持ちはわかります。
しかし行っていなければ2度と取り返しのつかない事態にもなります。
逆に言えば行ってあれば不本意な事態から器を守ってくれる魔法の方法でも
あるのです。
是非、何のために行うのか、ご理解頂いた上で作業に取り掛かって下さい。
拙著「金繕いの本」のP.24に、詳しい手順を掲載しております。
運搬兼用の室
工房で本漆の受講を始めた方が、とても良い工夫をされていたので
ご紹介致します。
持ち運び兼用の室です。
大きなダンボール箱の中に小さいダンボール箱を伏せて入れてあります。
それをお持ちの器に合わせてくり抜き、器をセット出来るようになって
います。
これで安定して器を持ち運び出来ます。
ご自宅では湿らせたタオルを入れて、このダンボールがそのまま室に
変身するそうです。
これは工房まで車でお出でになるメリットを最大限に生かした方法でしょう。
当工房ではスペースの関係上、器はお預かりしておりません。
しかしお持ち帰りになって頂くことで、ご自身で漆を固化させる方法を
覚えられます。
また接着の際にもズレないようにしっかりチェックが出来ますので、完成度
も高まると考えています。
お納めしました
先日お納めした金繕いの依頼品を、ご紹介致します。
まずは練り込みのお皿です。
かなりバラバラに割れてしまっていました。
練り込みとは色の異なる粘土を練り合わせて模様を作る技法のこと
で、金太郎飴を想像してもらえばわかりやすいと思います。
お預かりしたお皿は、練り込みが小花柄のように見える可愛らしいものです。
これに金泥の仕上げがとても映えました。
破損上、仕上げが太くなってしまったところは、練り込みの線が続くように
銀泥でラインを入れてあります。
これが持ち主の方に好評だったそうで、一安心しました。
次もお皿の割れです。
こちらは直径25cmほどの陶器です。
仕上げを釉薬の感じに合わせて硫化した銀箔を使いました。
1箇所だけ、黄色の斑点のところは金箔に変えてあります。
どちらもちょっとした工夫ですが、程よく馴染ませた感じが成功して
いるのではないかと思います。
拭き漆大会拡大中
よみうりカルチャーセンター大宮教室での拭き漆大会は継続・
拡大しています。
それぞれの方で気に入った木地を探されて、挑まれています。
木地の入手先ですが、探しやすいのは漆材料のお店だと思います。
木地を専門にしている業者さんもおられますが、ネットで検索しやすい
という点では漆材料店になるかと思います。
拭き漆向きと明記されている場合もありますが、木目が綺麗なものを
選ばれるのが良いかと思います。
ケヤキを思い浮かべて頂けるとわかりやすいのではないかと思いますが、
他にも木目が美しい樹種はありますので、お好みのものを見つけて
みて下さい。
漆を塗り重ねる度に、どんどん美しさが増すので、ハマってしまう方が
拡大中です(笑)
目から鱗の質問2
昨日に引き続き、目から鱗の質問です。
金繕いの講座の見学にお出でになった方から「使えますか?」と
質問がありました。
この質問にはとっさに「使うために直しています。」とお答えして
しまったのですが、よくよくお話を聞くと仕方のない質問だった
のです。
というのもこの方は割れた器を瞬間接着剤で接着されていた為、何度も
剥離してしまうことを繰り返されていたのです。
拙著「金繕いの本」にも記載していますが、瞬間接着剤で接着してしまうと
不本意な形で接着されてしまうので、剥離して金繕いした方が綺麗に
仕上がります。
もう一つの問題が、見学に来られた方が体験したように剥離することにあります。
これは接着剤全般が耐熱温度が60度しかないからです。
よって熱い飲み物を入れる器に顕著に現れます。
剥離する度に接着し直していると断面に接着剤の残りが蓄積し、ますます
接着強度が落ちます。
これは悲しい話です。
「使えますか?」というご質問が出るのも当然です。
「また使いたい」というのが金繕いの原点です。
その言葉に改めて気がつかせてくれた質問でした。