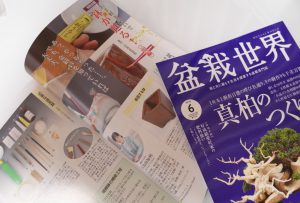月別アーカイブ: 2018年5月
ふたもん 塩の壺
「おむすびまるさんかく」と陶芸家の鹿児島睦さんがコラボレーション
した「ふたもん 塩の壺」が届きました。
温かみのあるぽってりした形の壺です。
蓋には鹿児島さんのイラストがレリーフになっています。
中に入っているのは「鳥海 海の泉の塩」です。
海水と伏流水が交わる場所から海水を汲み上げて塩にしたものだそうで、
まろやかな甘みが素材の旨みを引き出すようです。
「おむすびまるさんかく」さんのセレクトですから間違いありません。
これがグレーの壺の中に入ると、塩の白が冴えて見えるように計算されて
いるのです。
パッケージも好みです。
残念ながら対になっている「梅干しの壺」はSOLD OUTして
いたのですが、再入荷の予定があるそうです。
こちらは白い壺で、蓋のレリーフ柄も違います。
きっと白に梅干しの色が綺麗に見えるでしょう。
楽しみに待っています。
盆栽世界7月号 校正終了
先般からお知らせしている「盆栽世界」の7月号ですが、
6月4日発売に向けて既に校正が完了しています。
今回は磁器赤絵鉢のヒビ止め+接着です。
見ていただきたいのが、
ヒビ+接着の流れ
鉢の内側から外側まで通った貫通穴の塞ぎ方
和紙を使用した補強の仕方
です。
特に貫通穴と和紙による補強は「金繕いの本」にも掲載していない
技術です。
何より前月同様、詳細な説明は、S編集長がこの特集に真摯に取り
組んで下さったことがよくわかります。
またS編集長ならではの観点と思われるコラムの内容は、初心者に
とても参考になる事柄が取り上げられています。
是非、雑誌を手に取ってご覧下さい。
カラーコピーではなく。
大きい欠けの仕上げ
NHK文化センター 千葉教室のNさんの作品をご紹介致します。
大きい欠けの仕上げをなさいました。
最大の幅が3cm弱ある欠けです。
ご本人は蒔下の弁柄漆が厚くなってしまったとおっしゃっていますが、
釉薬がぽってりした陶器の感じと合っているので、違和感はありません。
こちらはこの後、銀泥で縞を入れる予定です。
この小皿は欠けが大きいだけでなく、縁が緩く波があり、形を作る
こと自体が難しい欠けでした。
まずきちんと形を作られてから仕上げに挑まれたので、大変完成度が
高い作品になっています。
よく金繕いした方が良くなると言われますが、この小皿もその例で、
元々の草花柄と呼応するように見えます。
大きい欠けの仕上げをする方法はいくつかありますが、今回Nさんは
太めの筆を使うことを選択されました。
筆に弁柄漆を含ませる量が難しいのですが、これは使っているうちに
慣れるしかありません。
今回これだけの完成度なので、じきに慣れられると思います。
以前のブログにも書きましたが、道具は腕を助けます。
なさりたい内容によって適切な道具を選択下さい。
輝和美倶楽部 懇親会での展示
先日、1日講座を行った輝和美倶楽部さんの懇親会で作品の
展示をさせて頂きました。
「金繕いの本」の他、雑誌やWEBマガジンに紹介した物に未発表の
2作品を入れて10点展示させて頂きました。
輝和美倶楽部さんは、日本の文化を楽しみ、交流しながら体験できる場
(コミュニティクラブハウス)として設立されています。
ご興味がおありになる方々に見て頂けて、いい機会になりました。
また講座を計画していますので、決まりましたら、このブログでもお知らせ
したいと思います。
ところで会場は代官山駅近くの古い日本家屋を改装したスペースでした。
和のお庭と和洋折中になっている空間が素敵でした。
都会の代官山にぽっかり‘日本’が存在している様が、建物好きとしては
興味深々でした。
スワロフスキーもOK!
先日、金箔を貼った貝合わせには金マジックで色々な物が
合うのではないかと提案したところ、スワロフスキーも
合うのでは?とNHK文化センター ユーカリが丘教室の
Mさんが持ってきて下さいました。
スワロフスキーのタイプライターと香水瓶です。
拝見して思わず「かわいい!」と言ってしまったほどの品です。
どちらも金がワンポイントに使われているので、貝合わせに違和感が
ありません。
Mさんは洋風のものでも合いますねとおっしゃいましたが、その
通りです。
教室の方々からも「これなら通年飾れるのでは?」等々、賛同の声が
上がりました。
どちらもしまっておられた物なのだそうですが、そのようなものが
貝合わせによって使われるのは嬉しいことです。
これも一種の金繕いかもしれません。
モダンな貝合わせ
NHK文化センター柏教室のTさんの作品をご紹介致します。
金箔が光ってしまって、見にくい画像ですみません。
金箔を貼った上にフリーハンドで線を描き、金泥と銀泥を蒔いた
大変モダンなデザインです。
金、銀の光沢違いで見せるところも、面白い選択です。
貝合わせというと花鳥風月を描かれる方が多いので、このような
モダンなデザインはとても斬新です。
まだまだTさんにはモダンデザインの構想がたくさんありますので、今後
の制作も楽しみにしています。
萩焼小皿揃い
NHK文化センター柏教室のHさんの作品をご紹介致します。
萩焼の小皿の揃いの欠けを金繕いされました。
銀泥で仕上げられています。
一つ一つ欠けの大きさ、形、位置が違うので、5つで見ると楽しめる
のが金繕いの面白いところです。
こちらはご友人からの預かり物なので、返却されます。
Hさんとしては銀泥が少々硫化したところで完成としたかったので、
人工的に硫化する方法を選択されました。
このように預かり物ですと好みの感じに硫化したところで、もう一度
お預け願うのは難しい場合があります。
人工的に硫化する方法も会得しておくと良いかと思います。
ご希望の方は教室でご確認下さい。
藍 不作
先般、順調に発芽しているとブログに書いた藍ですが、
連休明けの寒さの影響で稀に見る低発芽率となってしまいました。
保証発芽率が70%なのですが、これを切りました。
藍を育て始めて、こんなに低いのは初めてです。
最終的には6株あれば良いので問題はないのですが、少々衝撃的
な出来事です。
発芽した芽を大切に大きくしようと前向きに考えているところ
です。
レモン絞りの把手
藤那海工房の金繕い教室・Oさんの作品をご紹介致します。
レモン絞りの把手の接着です。
当初は接着して形になっていれば良いとのご意向だったのですが、
微妙な角度の接着が難しかったのです。
そこで断面に軸を入れ、接着して頂きました。
Oさんは道具箱を始め、作業の工程でもいろいろ工夫される方です。
軸を入れる際にもオリジナルの治具を作って作業されていました。
それがとても素晴らしいものなので、同様の作業をされる方には
ご紹介したいと思います。
途中の作業は苦労されましたが、様々な技術も経験されましたし、
結果的にしっかりした接着になったことで満足の完成度になったのでは
ないでしょうか。
現在、Oさんは藤那海工房で本漆の金繕いにもチャレンジなさっています。
元々本漆の金繕いのご経験があるので、私共の方法にも興味を持って
取り組んで下さっています。
盆栽世界6月号 残り僅か
今月2日に発売になった雑誌「盆栽世界」6月号に
焼締鉢のヒビ+欠けの金繕いハウツーを掲載して頂き
ました。
各教室で講座の度に内容をご紹介させて頂いておりますが、その
内容の濃さが大変好評です。
私の手元にお譲り出来る分を確保していましたが、おかげさまで
残数が僅かになって参りました。
もし取り置きをお望みの方がおられましたら、お手数ですがメールで
ご依頼下さい。
書店でも取り扱いがありますが、すでに購入出来なかったとの情報も
入っております。
来月7月号は赤絵磁器鉢の割れの接着とヒビ止めの他、「金繕いの本」
でも紹介していない補強のテクニックや、難しい破損を埋める方法を
掲載する予定です。
こちらもお楽しみに!
※おかげさまで私の手元にある6月号は完売致しました。(5/21)
まだAmazonなどでは入手可能です。
ぜひお求め下さい。